近年、インターネット上を中心に、外国人観光客に対する排斥的な言論が目立つようになりました。「日本が嫌なら母国に帰れ」といった過激な言葉も飛び交い、社会問題となっています。このような排斥論の背景には、日本の歴史や国民性が深く関わっていると考えられます。
目次
外国人観光客排斥論の現状
江戸時代の「異人」に対するまなざし
排斥論の根底にある「内」と「外」の意識
現代社会の歪みが排斥論を増幅させる
多様性と共生社会の実現に向けて
1. 外国人観光客排斥論の現状
新型コロナウイルス感染症の流行以降、外国人観光客の入国が制限され、日本の観光業界は大打撃を受けました。しかし、水際対策の緩和とともに外国人観光客が再び増加し始めると、ネット上では「観光客が増えすぎて迷惑」「マナーが悪い」といった批判的な意見が目立つようになりました。
2. 江戸時代の「異人」に対するまなざし
江戸時代、日本は鎖国政策をとり、外国との交流を制限していました。しかし、オランダや中国との貿易は細々と続けられ、 Nagasaki など一部の港では外国人が滞在していました。当時の日本人にとって、外国人は「異人」であり、警戒の対象でした。
3. 排斥論の根底にある「内」と「外」の意識
このような「異人」に対する警戒心は、現代の日本人にも受け継がれています。日本人は、自分たちを「内」、外国人を「外」と区別する意識が強く、その境界線を曖昧にすることを嫌う傾向があります。外国人観光客の増加は、この「内」と「外」の境界線を揺るがすものとして捉えられ、排斥論につながっていると考えられます。
4. 現代社会の歪みが排斥論を増幅させる
現代社会は、グローバル化が進み、人々の交流がますます盛んになっています。しかし、一方で、経済格差の拡大や雇用不安など、社会の歪みも深刻化しています。このような状況下で、外国人観光客の増加は、一部の人々にとって脅威となり、排斥論を増幅させる要因となっていると考えられます。
5. 多様性と共生社会の実現に向けて
外国人観光客の排斥論は、日本の国際的なイメージを損なうだけでなく、多様性と共生社会の実現を妨げるものです。私たちは、歴史や国民性を理解しつつ、現代社会の課題にも向き合い、外国人観光客との良好な関係を築く必要があります。そのためには、相互理解を深めるための教育や、多文化共生社会に向けた政策が不可欠です。
まとめ
外国人観光客排斥論は、日本の歴史や国民性、そして現代社会の歪みが複雑に絡み合って生じている問題です。この問題を解決するためには、多様性を尊重し、共生社会を目指すための取り組みが求められます。

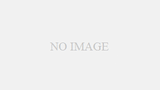
コメント