直木賞作家、朝井まかてさんによる『秘密の花園』(日本経済新聞出版)は、長編伝奇小説『南総里見八犬伝』の作者、曲亭馬琴の生涯を描いた歴史小説だ。2024年秋には映画『八犬伝』が公開され、2025年は江戸の出版人、蔦屋重三郎(つたやじゅうざぶろう)を主人公とするNHK大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』も始まり、江戸文化への注目が高まる。朝井まかてさんのインタビュー第3回は、歴史小説を書くということについて。
プロットは作らない
以前、インタビューで、朝井さんが「歴史小説を書く際には事前にプロット(設計図)を作らずに書いている」と話されているのを読みました。朝井さんはどのようにして歴史小説を書いているのですか?
歴史小説だけではなく、フィクションの時代小説でも事前にプロットを作らないです。いつからこうなってしまったのか(笑)。性格なんでしょうか。決まった道を歩けないと言おうか、へそ曲がりなんでしょう。
ただ、年表は作ります。その時代の政治事件も含めて、主人公がどんな世界を生きていたかは大切にしているつもりです。実在の人物を主人公にする場合は、その人の足跡が確かに残っているのですから。
馬琴の場合はあまりにも著作数が多くて、いくつのときにどの作品を書いたかを把握するだけでも相当なエネルギーを費やしました。でもそうすることで、だんだん呼吸が合ってくるというか、主人公と気が合ってくるんですね。
たとえば、馬琴の妻・百(ひゃく)が「兄夫婦の体の弱い子どもを引き取った」という事実から、百はこれまで言われてきた悪妻とはちょっと違うのでは、馬琴と百の夫婦関係はこうだったのではないかと想像しました。百が版元に馬琴の悪口を言うシーンなどは、私もノリノリで(笑)。
晩年、馬琴の目が次第に見えなくなっていく。不安が高まる。それでも書き続けなくてはならない。書き続けたい、『八犬伝』を完成させたい。
書き手としては身につまされるんですよ、ほんとに。半ば泣きそうになるのをぐっと堪えて、私自身の感情を流れ込ませると過多になるので、馬琴はこうであろうと想像するスタンスを維持しながら書きました。ときに馬琴と対話しながら。すると、物語は動いていきます。
『秘密の花園』を執筆するにあたって私なりのチャレンジの一つは、馬琴の書いた作品の一部を物語に取り入れたことです。現代語訳にすることも考えたのですが、どうも違う。音律が違うので。そこで馬琴の文体が持つ味わいをできるだけ生かして、当時の言葉や馬琴が選んだ言葉を用いて再現しました。そうしないと、行間から香るものを残せないと思いましたから。現代ではすでに滅びてしまった言葉や言い回しも多いので読者には不親切かもしれませんが、そこは「えいやっ」でした。どうか、伝わるものがありますように、と。
でも実はコツがあって、音読すると身体に入ってくるんです。感情や景色が入ってきます。
山田風太郎の『八犬伝』も意識されましたか?
山田風太郎の『八犬伝』はずいぶん昔に読み、おぼろげに覚えているぐらいです。先行作品はたくさんあるので、敬意を持ちながらも、意識することはほとんどありませんね。
歴史小説は同じ史料を使うこともあるので、「同じだ」と指摘されるのを恐れるあまり、意識して変えるのもおかしい。『南総里見八犬伝』の引用においても、私が盛り込みたいと思った部分を取り入れています。また、馬琴の人生のどこを描くかも、作家によって違ってきます。私は馬琴の幼少時代も詳細に描きました。彼の人生にとって非常に大きな意味を持つからです。
たくさん書くのは日本の伝統
馬琴と同様、朝井さんは数多くの作品を書かれていますね。
49歳の遅いデビューということもあり、今も連載を複数抱えて休みなしに書き続けています。ありがたいことです。そもそも書くことが好きなんですね。書いているときがいちばん自分でいられるというか、書く瞬間の積み重ねこそが作家であると思うので。
締切前はいつもどんよりしてるんですけどね。気が重くて。いつも、今度こそアカンかも、書けないかもと蒼(あお)くなってますから。
もっと計画的にやればいいのに、だめなんですよね。計画とか目標を立てるとかができない。いずれは一作品ずつ書くようにギアチェンジするんでしょうけど、たくさん書くことは日本の戯作(げさく)の伝統だから、とも思っています。江戸時代から続く文芸の歴史が連綿と続いていて、そのはしくれに私もいるのだと自分を励ましたりして。
馬琴との共通点ということで言えば、朝井さんも校正を3回、4回と重ねるタイプですか?
江戸時代の出版工程の大変さは、今とはまったく違います。版木を一枚一枚手彫りするんですから。彫師など多くの職人がかかわり、彫り間違い、それ以前の段階で筆耕(清書)の間違いもあった。初校で修正したはずの箇所が再校ではなぜか欠けている、ということも起きるわけで。だから馬琴をはじめこの時代の作家は、三校、四校まで入念にチェックすることが当たり前でした。
私も校正は念入りなほうだと思います。馬琴は有識者にケチをつけられるのがとにかく嫌で、間違いを指摘されるとカーッとなって反論しています。私の場合はそこは居直ってる(笑)。ただ、ひとたび作品が世に出たら、その作品は読者のものになる。だからその前にやれる限りのことをやらせてもらいたいし、作品世界に尽くしたいという気持ちがあります。あ、馬琴も本音はきっとそうだったでしょうね。
新作は「農」がテーマ
新作の 『青姫』 (徳間書店)について伺います。『秘密の花園』とはまったく異なる作品のようですが、どういう物語なのですか?
ちょうど新型コロナウイルス禍の時期に連載をスタートしたもので、土が恋しくなりまして。そもそも植物が好きで、デビュー作も江戸時代の園芸をテーマに書いた小説です。でも「農」にはまだ挑んでなかったので、「農の芸」について書いてみよう! と。
舞台は江戸初期、戦国時代の気風がまだ残っていて、徳川幕府が海禁政策を取る前の、時代のはざまです。そこで、主人公の若者と共に生きてみようと思いました。
主人公が迷い込むのは、ある山間の郷(さと)。中世の堺のような自由経済の郷で、農業を行っておらず、不思議なルールで成り立っている秘境です。主人公はそこでお米を作らされることになり――。
郷は民による合議で自治しています。住人はクセの強い曲者揃いで、そこは笑って楽しんでいただけると思います。ただ、「農」を書くことは「土地」を考えることでもありました。開墾して農作物を作るという行為によって、土地に価値がつく一方、そこから離れられなくなる。書き手としては、企まずして、土地は、領土はいったい誰のものかを考えることになりました。
連載終了後まもなく、ロシアのウクライナ侵攻が起きました。自由の持続がいかに難しいか、もし攻め込まれたら自分はどうするか。物語には「屈するか、逃げるか、戦うか」をクジで決める場面が出てきます。それは天意に委ねるという昔ながらの運命の決め方ですが、クジを引くのは自分です。唯一、自分の運命にかかわる瞬間は息を詰めて書いていました。
ファンタジー小説? と思われる要素をあえて盛り込みましたが、実は史実もかなり汲んでいます。お米の作り方については、江戸初期の史料はあまり残っていません。中期以降の史料や伝統的な農法を実践している農家での稲刈り体験、あとはひたすら想像です。
作中、丸い形の田んぼをフィクションで出しましたが、これも連載終了後、長崎の方に丸い田んぼが残っていることを知り驚きました。まるで細胞のような形をしていて、古代は渦巻き状にぐるぐると植えていたようです。
小説を書いていると、時折そういうことが起きるのが面白いです。これがあるからやめられません。
取材・文/金澤英恵 構成/桜井保幸(日経BOOKプラス編集) 写真/小野さやか

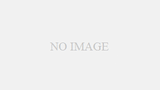
コメント